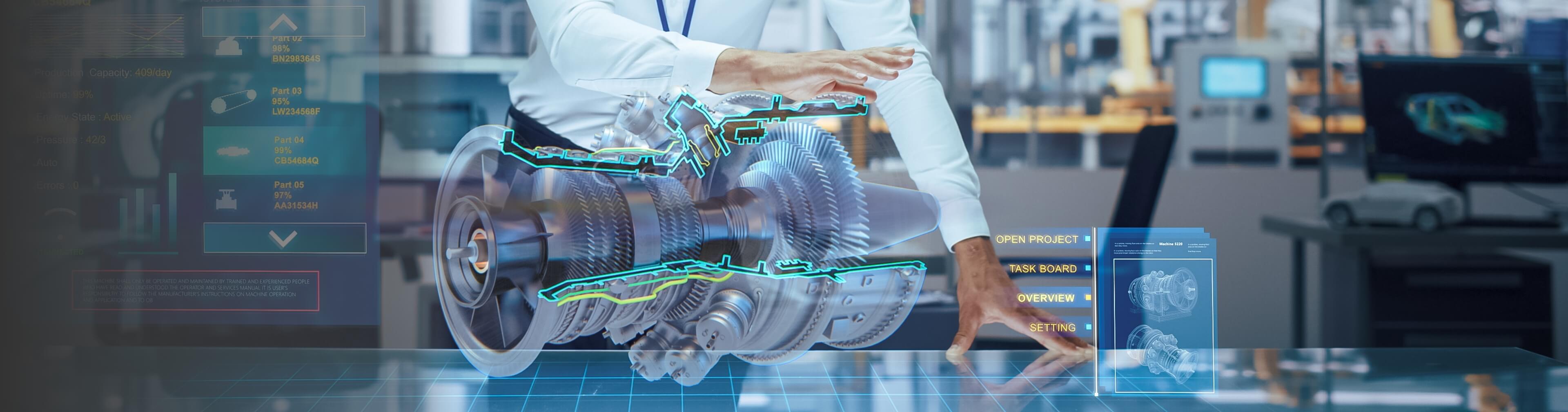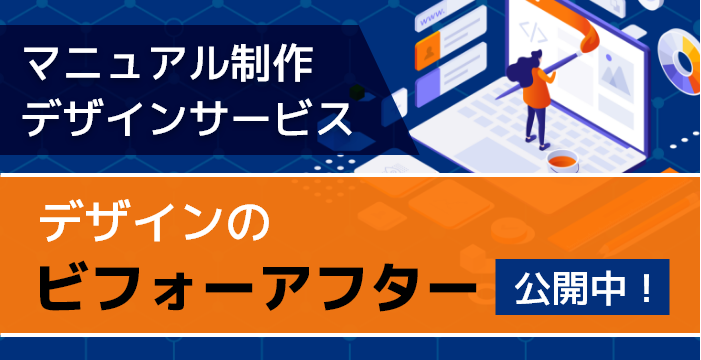二重派遣とは?違法となるケースや罰則、防止策を分かりやすく解説
2025.8.26

企業の人材活用において、労働者派遣は有効な手段の一つですが、その運用を誤ると「二重派遣」という違法行為に該当する可能性があります。二重派遣は、派遣労働者の権利を脅かし、企業の信頼を損なう重大なコンプライアンス違反です。
ここでは、二重派遣の基本的な定義と、法律で禁止されている理由について解説します。
目次
二重派遣とは?法律で禁止されている理由

労働者派遣は企業の人材活用において有効な手段ですが、運用を誤ると「二重派遣」という違法行為に該当する恐れがあります。
二重派遣は、派遣労働者の権利を脅かし、企業の信頼を損なう重大なコンプライアンス違反です。まずは、二重派遣の定義と禁止されている理由を見ていきましょう。
二重派遣の基本的な定義
二重派遣とは、派遣元事業主(派遣会社)から労働者の派遣を受けた派遣先企業が、その派遣労働者を別の企業に再度派遣し、再派遣先の指揮命令下で業務に従事させることを指します。
派遣契約の当事者でない企業が派遣労働者を指揮・管理することになるため、法律で厳しく禁止されています。
労働者の権利を守るための法律
二重派遣が禁止される最も大きな理由は、派遣労働者の雇用責任の所在が曖昧になるためです。労働契約は派遣元企業と結ばれているため、賃金の支払いや社会保険、労働災害が発生した際の責任は派遣元が負います。
しかし、二重派遣の状態では、実際に業務を指揮している再派遣先と労働者の間に直接の契約関係がなく、問題が発生した際に誰が責任を負うのか不明確になります。このような責任の所在の曖昧さは、労働者の権利が保護されない危険な状況を生み出すため、法律で禁止されています。
中間搾取の排除
二重派遣は、労働基準法第6条で禁止されている「中間搾取」に該当します。中間搾取とは、法律に基づかずに他人の就業に介入して利益を得る行為です。
二重派遣では、本来発生しないはずの仲介手数料などが派遣先によって上乗せされ、その結果として派遣労働者の賃金が不当に低くなる可能性があります。労働者が提供した労働に対して正当な対価が支払われなくなる事態を防ぐため、二重派遣は厳しく禁じられているのです。
参考:e-GOV「労働基準法」第六条二重派遣に科される厳しい罰則

二重派遣は法令違反に該当し、発覚した場合には「職業安定法」および「労働基準法」に基づき、厳格な罰則が科される可能性があります。違反企業は、法的責任を問われるだけでなく、社会的信用の低下や取引先との関係悪化といった重大なリスクを伴います。
企業としての信頼性を維持するためにも、適切な契約管理と現場運用が不可欠です。
職業安定法に基づく罰則
職業安定法第44条では、労働者供給事業を原則として禁止しています。
二重派遣は、この労働者供給事業に該当する行為と見なされます。違反した場合、同法第64条に基づき、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
この罰則の対象は、労働者を供給した派遣先企業と、二重派遣であることを知りながら労働者を受け入れた再派遣先企業の両方です。
参考:e-GOV「職業安定法」第四十四条、第六十四条労働基準法に基づく罰則
労働基準法第6条は「中間搾取の排除」を定めており、二重派遣はこの規定に違反します。これに違反した派遣先企業には、同法第118条に基づき、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。職業安定法とは異なり、こちらは主に中間搾取を行った派遣先企業が罰則の対象となります。
参考:e-GOV「労働基準法」第六条、第百十八条| 法律名 | 罰則内容 | 対象企業 |
|---|---|---|
|
職業安定法 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
派遣先企業、再派遣先企業 |
|
労働基準法 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
派遣先企業 |
二重派遣と混同されやすい契約形態

二重派遣の判断を難しくする要因の一つに、他の契約形態との混同があります。
特に「偽装請負」「業務委託」「出向」は、実態によっては二重派遣と見なされる可能性があるため、その違いを正確に理解しておくことが重要です。
偽装請負との明確な違い
偽装請負とは、契約形式上は「請負契約」でありながら、実態が「労働者派遣」である状態を指します。請負契約の場合、発注者から業務の進め方について具体的な指揮命令は受けません。
しかし、偽装請負では、発注者が請負会社の労働者に対して直接、業務の指示を出しています。これが二重派遣と結びつくと、派遣労働者が請負契約の現場で、発注者から直接指揮命令を受けるという複雑な違法状態に陥るケースがあり、特に注意が必要です。
参考:厚生労働省|派遣スタッフ活用のポイント業務委託・準委任契約との相違点
業務委託契約や準委任契約も、特定の業務を外部に委託する契約ですが、労働者派遣との最も大きな違いは「指揮命令権の有無」です。
業務委託や準委任では、委託元の企業が受託企業の労働者に対して直接指揮命令を行うことはありません。もし、準委任契約で受け入れた技術者を、契約に含まれていない別の企業のプロジェクトに参画させ、その企業の指揮命令下で働かせた場合、二重派遣に該当する可能性があります。
出向との違いと注意点
出向とは、労働者が元の企業との雇用契約を維持したまま、関連会社などで長期間就業することです。出向の場合、出向先の指揮命令下で業務を行いますが、これは労働者本人の同意を得た上での適法な人事異動です。
しかし、派遣労働者を本人の同意なく、業務命令として関連会社などに出向させることはできません。これは実質的な二重派遣となります。
こんなケースは要注意!二重派遣の具体例

意図せず二重派遣の状態に陥ることを避けるためには、具体的な事例を知っておくことが有効です。
特にIT業界や取引先との関係、グループ会社間のやり取りでは注意が必要です。
IT業界で起こりがちな多重下請け構造
IT業界では、大規模なシステム開発プロジェクトなどで、元請けから二次請け、三次請けへと業務が再委託される多重下請け構造が常態化しています。
このような現場に派遣された技術者が、派遣契約を結んでいる企業ではなく、上位の請負企業やクライアント(発注者)の担当者から直接、業務の指示を受けている場合、二重派遣に該当する可能性があります。
取引先企業での業務
自社で受け入れた派遣社員を、人手不足の取引先に手伝いに行かせるようなケースも危険です。
たとえ善意からであったとしても、派遣社員が取引先の社員の指揮命令下で業務を行った場合、それは二重派遣と見なされます。業務の場所がどこであれ、指揮命令権が誰にあるかが重要な判断基準となります。
グループ会社間での人材の融通
親会社が受け入れた派遣社員を、子会社の業務が多忙であるという理由で手伝いに行かせるなど、グループ会社間で安易に人材を融通することも二重派遣のリスクをはらみます。
この場合も、子会社の管理者が派遣社員に直接指示を出していれば、違法行為に該当します。
安心して活用できる!二重派遣に該当しないケース

二重派遣に該当するか否かの判断は、指揮命令系統がどこにあるかで決まります。
たとえ派遣先以外の場所で就業していたとしても、契約上の派遣先企業が適切に指揮命令を行っていれば、違法とはなりません。
ここでは、二重派遣に該当しない安心なケースについて具体的に解説します。
派遣先が明確に指揮命令している場合
派遣労働者の就業場所が、契約上の派遣先企業のオフィスではない場合があります。
例えば、派遣先企業が請け負ったプロジェクトのために、クライアント企業内で業務を行うケースです。
このような場合でも、派遣先企業の社員が現場に常駐し、その社員が派遣労働者に対して明確に指揮命令を行っていれば、二重派遣にはあたりません。あくまでも、労働者派遣契約に基づいた指揮命令系統が維持されていることが重要です。
自社を守る!二重派遣を防ぐためのチェックポイント

二重派遣は「知らなかった」では済まされない問題です。自社が加害者になることを防ぎ、コンプライアンスを遵守するために、以下のポイントを常に確認する体制を整えましょう。
契約書の内容を詳細に確認する
まず基本となるのが、派遣元企業と交わす労働者派遣契約の内容を詳細に確認することです。
指揮命令者、就業場所、業務内容などが明確に記載されているかを確認します。特に、業務内容が曖昧であったり、実態と乖離したりすることがないように注意が必要です。請負契約や業務委託契約など、他の契約形態と混同しないよう、契約形態を正確に理解することも不可欠です。
指揮命令系統が誰にあるか明確にする
現場で最も重要なのが、指揮命令系統の明確化です。派遣労働者に対して、誰が業務の指示を出す権限を持っているのかを、関係者全員が正しく認識する必要があります。派遣先の責任者以外の人物が、安易に指示を出していないか、定期的に確認することが求められます。
| チェック内容 | 確認内容 |
|---|---|
|
契約内容の確認 |
労働者派遣契約か、請負契約か。指揮命令者、業務内容が明記されているか。 |
|
指揮命令者の確認 |
実際に誰が指示を出しているか。契約上の指揮命令者と一致しているか。 |
|
就業場所の確認 |
派遣先以外の場所で業務を行う場合、派遣先の管理者が指揮命令を行っているか。 |
|
派遣会社との連携 |
契約内容の変更が必要な場合、事前に派遣元に相談しているか。 |
派遣会社と密に連携する
業務内容の変更や就業場所の変更など、契約内容に関わる事態が発生した場合は、必ず事前に派遣元である派遣会社に相談し、必要な手続きを踏むことが重要です。
派遣会社は労働者派遣の専門家であり、法的な観点からのアドバイスを提供してくれます。日頃から密なコミュニケーションを取り、良好なパートナーシップを築くことが、トラブルの未然防止につながります。
もし二重派遣が疑われる場合の対処法

細心の注意を払っていても、二重派遣の疑いが生じてしまう可能性はゼロではありません。万が一、そのような事態に気づいた場合は、迅速かつ誠実に対応することが求められます。
速やかに派遣元の会社に相談する
自社の対応が二重派遣に該当する可能性があると気づいた場合や、派遣労働者から指摘を受けた場合は、速やかに派遣元企業へ連絡し、事実関係を正確に報告・相談することが重要です。
問題を放置したり、隠蔽を試みたりすることは、法的リスクや信頼の失墜につながりかねません。早期の是正対応が、企業としての信頼性を守る第一歩となります。
契約内容の見直しと是正措置を講じる
派遣元の会社と連携し、問題となっている状況を解消するための是正措置を講じます。
具体的には、指揮命令系統を契約通りに修正したり、実態に合わせて契約内容を見直したりするなどの対応が必要です。場合によっては、弁護士などの専門家の助言を求めることも検討しましょう。
まとめ:二重派遣のリスクを理解し健全な企業運営を
二重派遣は、派遣労働者の権利を侵害し、企業に法的な罰則や社会的な信用の失墜といった深刻なリスクをもたらす違法行為です。自社が意図せず違法行為に関与しないよう、二重派遣の定義とリスクを正しく理解し、契約内容や現場の指揮命令系統を常に確認することが不可欠です。
派遣会社との連携を密にし、コンプライアンスを遵守した健全な企業運営を心掛けましょう。
エンジニアとして働きたい人と、エンジニア不足にお困りの企業様をつなぐ
BREXA Technologyでは、IT分野だけでなく、機械・電気・電子などの技術領域にも対応した人材派遣を行っています。経験者はもちろん、未経験から育成されたエンジニアも多数在籍しており、幅広いニーズに応える人材をご紹介可能です。
技術職でのキャリアを目指す方も、企業の人材戦略を支援したい方も、ぜひご活用ください。