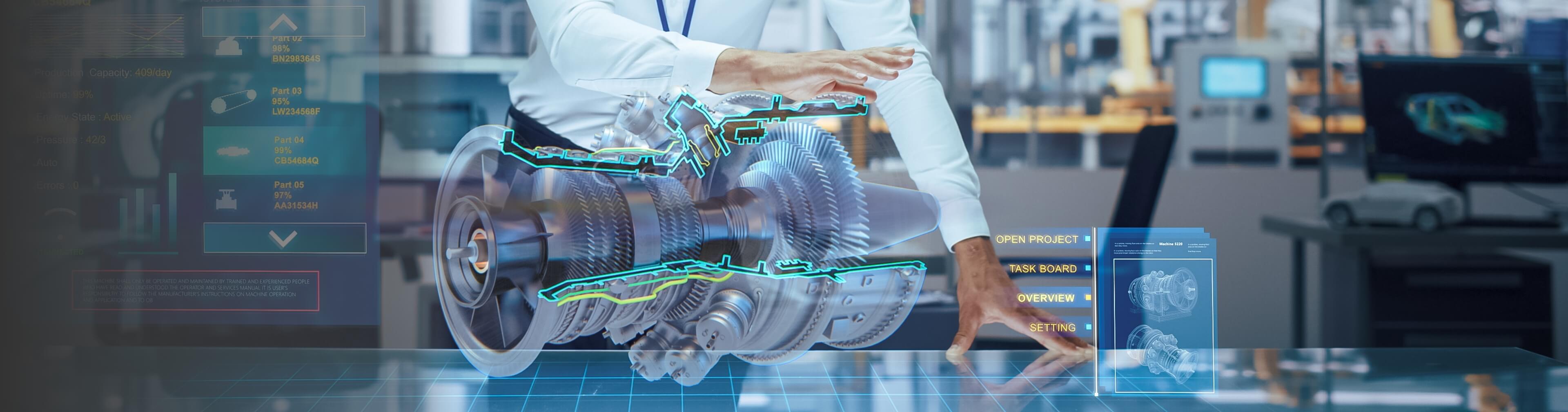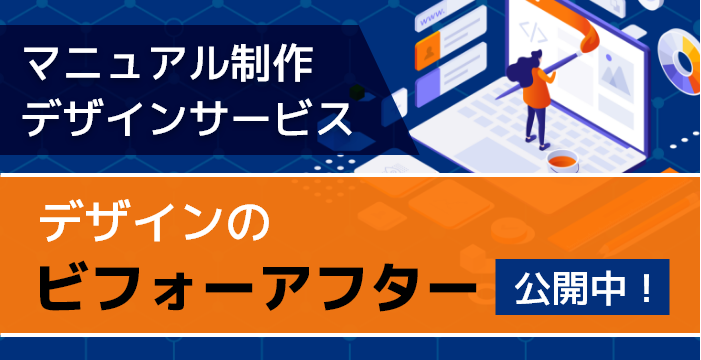インフラエンジニア外注の成功法!費用相場・依頼先の選び方を完全ガイド
2025.9.16

企業のITシステムが複雑化・高度化する中、「インフラを扱える人材が社内にいない」「専門スキルを持つ人材をすぐに確保したい」といった課題を抱える企業が増えています。
こうした課題を解決する手段の一つが、インフラエンジニアの外注です。
本記事では、インフラエンジニアの外注を検討している担当者様に向けて、依頼できる業務内容からメリット・デメリット、費用相場、そして失敗しないための外注先の選び方まで、網羅的に解説します。
目次
インフラエンジニアの外注とは?

インフラエンジニアの外注とは、企業が自社のITインフラに関する業務を、社外の専門家や企業に委託することです。
まずは、外注を理解する上で基本となる「インフラエンジニアの役割」と「外注で依頼できる具体的な業務」について解説します。
インフラエンジニアとは
インフラエンジニアは、ITシステムの基盤となる「インフラ」の設計、構築、運用、保守を専門とする技術者のことです。私たちが日常的に利用するWebサイトやアプリケーション、社内システムなどが安定して動き続けるためには、サーバーやネットワークといったITインフラが不可欠です。
インフラエンジニアは、この縁の下の力持ちとして、システムの安定稼働を支える重要な役割を担っています。その業務は、物理的なサーバーの設置から、クラウド環境の構築、セキュリティ対策まで多岐にわたります。
関連記事:エンジニアの種類を徹底解説!IT・機械・電気・化学系まで職種別に紹介
外注で依頼できる主な業務内容
インフラエンジニアの業務は幅広く、プロジェクトの各フェーズに応じて必要なスキルも異なります。
外注を活用することで、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保することが可能です。
| 業務フェーズ | 主な業務内容 |
|---|---|
|
設計 |
・要件定義 |
|
構築 |
・サーバー構築 |
|
運用・保守 |
・サーバー、ネットワークの監視 |
|
その他 |
・セキュリティ診断、脆弱性対応 |
スポット的な作業から継続的な運用保守まで、企業のニーズに合わせて柔軟に業務を依頼できるのが外注の大きな特徴です。
インフラエンジニアを外注するメリット
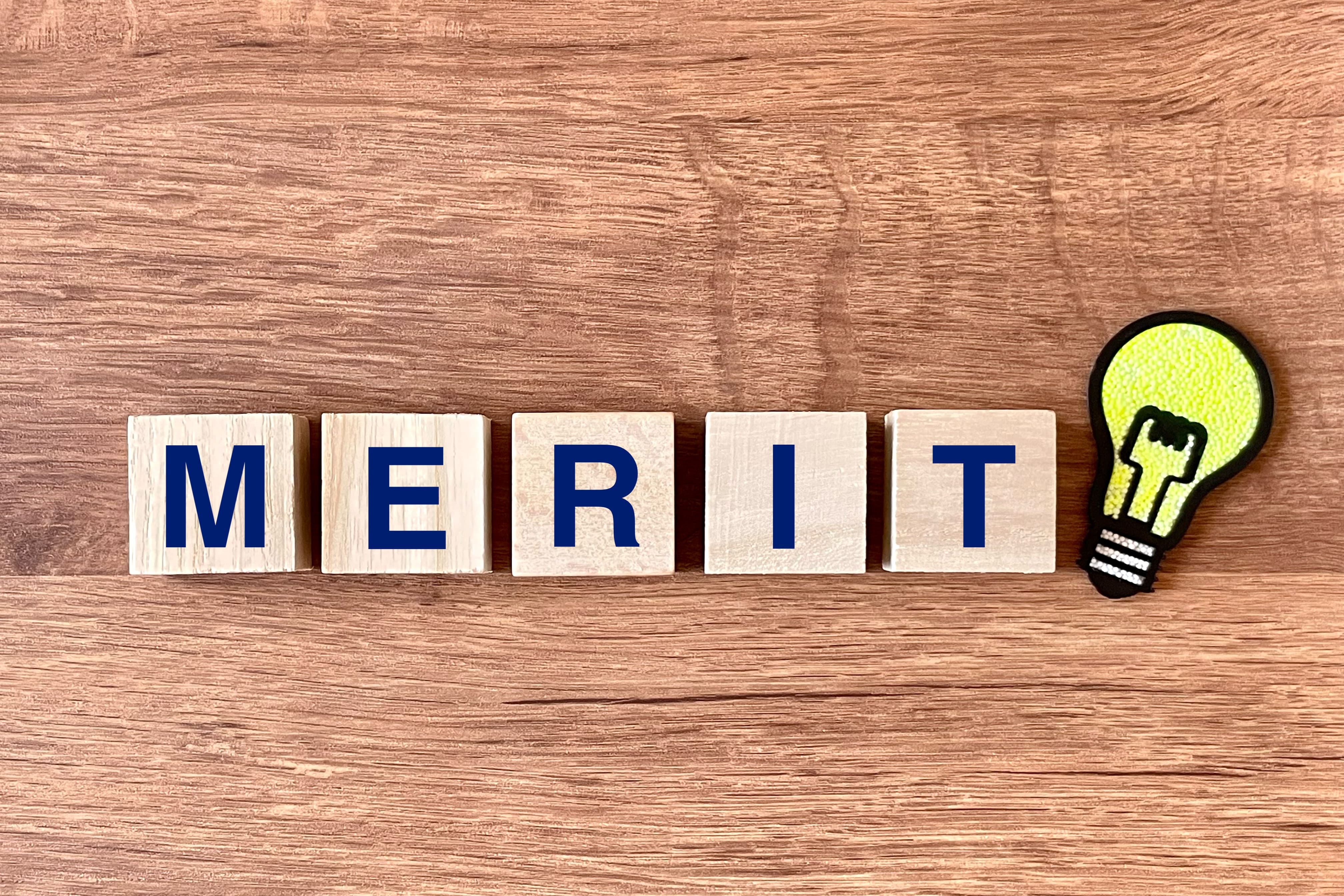
インフラエンジニアを外注することは、単なる人手不足の解消にとどまらず、企業経営に多くのメリットをもたらします。
ここでは、主な4つのメリットについて解説します。
コストを最適化できる
正社員としてインフラエンジニアを一人採用する場合、給与や賞与の他に、社会保険料、福利厚生費、教育研修費など、様々なコストが発生します。
外注であれば、これらの間接的なコストがかからず、必要な業務に対してのみ費用を支払うため、トータルコストを抑えることが可能です。特に、プロジェクト単位で専門人材が必要な場合や、短期間だけリソースを増強したい場合に、コストメリットは大きくなります。
高い専門性を確保できる
ITインフラの世界は技術の進歩が速く、特にクラウド技術やセキュリティ分野では、常に最新の知識とスキルが求められます。自社のエンジニアだけで全ての専門領域をカバーするのは容易ではありません。
外注を活用すれば、特定の分野で高い専門性を持つプロフェッショナルに業務を依頼できます。これにより、自社だけでは実現が難しかった高度なインフラ環境の構築や、堅牢なセキュリティ対策を実現できます。
リソースを柔軟に調整できる
ビジネスの状況に応じて、必要なエンジニアの人数やスキルは変動します。例えば、大規模なシステム開発プロジェクトの立ち上げ期には多くの構築担当者が必要ですが、運用フェーズに入ると少人数の監視担当者で十分な場合もあります。
外注であれば、プロジェクトの繁閑に合わせて契約内容を見直し、人員を柔軟に増減させることが可能です。これにより、常に最適なリソース配分を維持し、無駄な人件費の発生を防ぎます。
社員がコア業務に集中できる
システムの監視や定型的な運用・保守といったノンコア業務を外注することで、自社のエンジニアを、より付加価値の高いコア業務に集中させることができます。
例えば、事業戦略に直結する新サービスの企画・開発や、DX推進のための技術選定といった業務です。社員が本来注力すべき業務にリソースを割けるようになることで、企業全体の生産性向上と競争力強化につながります。
インフラエンジニアを外注するデメリット

インフラエンジニアの外注には多くのメリットがありますが、同時に注意すべきポイントも存在します。外注を成功させるためには、事前に潜在的なリスクを把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。
情報漏洩のリスクがある
社外の人間が自社のシステムや情報にアクセスするため、情報漏洩のリスクはゼロではありません。特に、顧客情報や機密情報などを扱うシステムを委託する場合には、細心の注意が必要です。
このリスクを低減するためには、契約時に秘密保持契約(NDA)を締結することはもちろん、委託先のセキュリティポリシーや実績を確認することが不可欠です。
コミュニケーションコストが発生する
外部のエンジニアに業務を委託する場合、社内メンバー同士のような「暗黙の了解」やスムーズな意思疎通は期待できません。そのため、業務の目的や範囲、技術的な要件などを正確かつ明確に伝えるためのコミュニケーションが不可欠です。
指示が曖昧だったり、認識のズレが生じたりすると、手戻りが発生し、結果的に余計な時間やコストがかかってしまう可能性があります。
このリスクを避けるためには、定期的な打ち合わせの実施や、業務内容を整理したドキュメントの共有など、円滑なコミュニケーションを支える仕組みづくりが重要です。
社内にノウハウが蓄積されにくい
外注に頼りすぎると、インフラに関する知識や障害対応のノウハウが社内に蓄積されにくいという問題があります。委託先のエンジニアが作業内容をブラックボックス化してしまうと、契約終了後に自社でシステムを運用できなくなったり、簡単なトラブル対応すらできなくなったりする恐れがあります。
これを防ぐためには、作業内容のドキュメント化を契約要件に盛り込んだり、定期的に自社エンジニアへの情報共有会を実施したりするなどの対策が有効です。
インフラエンジニア外注の費用相場
インフラエンジニアの外注を検討する際、多くの方が最初に気になるのが「費用」です。外注コストは、依頼する業務の内容や求めるスキルレベル、契約形態によって大きく異なります。
業務内容別の費用相場
一般的に、高度な専門性や上流工程の経験が求められる業務ほど、単価は高くなる傾向にあります。
| 業務内容 | 月額単価の目安 | 備考 |
|---|---|---|
|
サーバー・ネットワークの運用・保守 |
40~70万円 |
比較的定型的な業務が多く、経験の浅いエンジニアでも対応可能な場合がある |
|
サーバー・ネットワークの設計・構築 |
60~100万円 |
システムの根幹に関わる部分であり、相応の経験とスキルが求められる |
|
クラウド環境の設計・構築 |
70~120万円 |
AWS、Azure、GCPなどの専門知識が必要。特にIaCなどのスキルを持つエンジニアは高単価 |
|
セキュリティ対策・コンサルティング |
80~150万円 |
高度な専門知識と実績が求められ、企業の重要な資産を守る役割を担う |
契約形態別の費用相場
外注の契約形態は、主に「準委任契約」と「請負契約」に分けられ、費用の考え方が異なります。
■準委任契約
準委任契約とは、エンジニアの労働時間に対して報酬を支払う契約です。月々の稼働時間(例: 140〜180時間)を定め、その対価として月額報酬を支払うのが一般的です。
費用は「エンジニアの月額単価 × 稼働月数」で計算されます。
■請負契約
請負契約とは、成果物(例: 設計書、構築されたシステム)の完成に対して報酬を支払う契約です。費用は、プロジェクト全体の作業量や難易度から見積もられ、一括または分割で支払われます。
どちらの契約形態が適しているかは、依頼したい業務内容によって異なります。
仕様が固まっておらず、柔軟な対応が必要な場合は準委任契約、成果物が明確に定義できる場合は請負契約が向いています。
インフラエンジニアの外注先の種類

インフラエンジニアの外注先は、大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や状況に合わせて最適な依頼先を選びましょう。
フリーランスエンジニア
フリーランスエンジニアは、企業に所属せず個人で活動している技術者です。エージェントサービスやクラウドソーシングサイトを通じて探すことができ、直接契約することで中間マージンを抑えられるため、比較的コストを抑えやすいのが特徴です。
また、特定の分野に高い専門性を持つ人材を見つけやすく、ニッチな技術や短期プロジェクトへの対応にも適しています。
ただし、スキルや信頼性には個人差があるため、過去の実績や評価、コミュニケーション力などを慎重に見極めることが重要です。
SES(システムエンジニアリングサービス)企業
SES企業は、エンジニアの技術力を提供するサービスを展開しており、所属する正社員エンジニアが顧客企業に常駐して業務を行います。契約形態は主に準委任契約で、業務時間に応じた報酬体系が一般的です。多くのエンジニアが在籍しているため、必要な人材を比較的短期間で確保しやすいというメリットがあります。
ただし、エンジニアのスキルや経験には幅があるため、自社の業務内容や技術要件に合った人材を見極めることが重要です。事前の面談やスキルシートの確認を通じて、適切な人材を選定しましょう。
開発会社
開発会社は、システムの受託開発を中心に、インフラ構築も含めた一括対応が可能な企業です。アプリケーション開発とインフラ整備を同時に進めたい場合や、プロジェクト全体のマネジメントまで任せたい場合に適しています。
多くの開発会社では、品質管理や進行管理の体制が整っており、一定のクオリティが期待できる点が強みです。
ただし、対応範囲が広くなる分、費用は比較的高めになる傾向があるため、予算とのバランスを見ながら検討することが重要です。
外注先選びで失敗しないために

インフラエンジニアの外注を成功させるためには、信頼できるパートナーの選定が何よりも重要です。依頼先の選び方次第で、プロジェクトの成果やコスト効率に大きな差が生まれます。
ここでは、外注先選びで失敗しないために押さえておきたい4つのポイントをご紹介します。
実績や得意分野を確認する
まず、候補となる会社のウェブサイトや資料で、過去の実績を確認しましょう。
特に、自社が依頼したい業務内容(例: AWS環境構築、セキュリティ監視など)と同様のプロジェクト経験が豊富かどうかは重要な判断基準です。得意な技術領域や業界なども確認し、自社のプロジェクトとの相性を見極めましょう。
コミュニケーション能力を見極める
見積もり依頼や商談の段階で、担当者のコミュニケーション能力を注意深く観察しましょう。
こちらの要望を正確に理解し、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、レスポンスは迅速で丁寧か、といった点は、プロジェクトを円滑に進める上で非常に重要です。実際に業務を担当する予定のエンジニアと事前に面談させてもらうのも有効な方法です。
セキュリティ体制を確認する
情報漏洩のリスクを避けるため、外注先のセキュリティ体制は必ず確認しましょう。
プライバシーマークやISMS(ISO27001)といった第三者認証を取得しているか、社員へのセキュリティ教育は徹底されているか、などを確認します。具体的なセキュリティ対策について質問し、明確な回答が得られるかどうかをチェックすることも大切です。
複数の会社を比較検討する
最初から一社に絞らず、必ず複数の会社から提案や見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。
費用はもちろん、提案内容の質、担当者の対応、実績などを総合的に評価し、最も信頼できるパートナーを選びましょう。相見積もりを取ることで、費用の適正価格を把握することにもつながります。
インフラエンジニア外注の進め方

実際にインフラエンジニアへの外注を進める際の、一般的な流れを4つのステップで解説します。この流れに沿って進めることで、スムーズな発注が可能になります。
目的と依頼内容を明確にする
外注を成功させる第一歩は、「何のために外注するのか」「どのような課題を解決したいのか」といった目的を明確にすることです。
たとえば、「クラウド環境への移行を進めたいが社内に専門人材がいない」「24時間365日の監視体制を構築したい」といった具体的なニーズが挙げられます。
目的が定まったら、依頼したい業務の範囲を洗い出し、必要なスキルや対応期間を整理しましょう。あわせて、予算やスケジュールの目安も設定しておくことで、外注先との打ち合わせがスムーズに進みます。
外注先を選定し、見積もりを取得する
明確にした目的と要件をもとに、外注先の候補をリサーチします。企業の公式サイトや外注比較サイト、既存の取引先からの紹介など、複数のチャネルを活用しましょう。
候補がある程度絞れたら、RFP(提案依頼書)を作成し、具体的な提案と見積もりを依頼します。RFPには、業務範囲・スケジュール・予算感・求めるスキルなどを明記することで、より精度の高い提案を受け取ることができます。
面談を通じて担当者を見極める
提案内容と見積もりを比較した後は、候補企業との面談を実施し、さらに絞り込みを行います。面談では、提案の具体性や実現可能性を確認するとともに、担当者の対応力やコミュニケーションの質も重要な判断材料となります。
可能であれば、実際に業務を担当するエンジニアとも面談を行い、スキルや経験、過去のプロジェクト事例などを直接確認しましょう。現場レベルでの相性や信頼感を確かめることが、外注成功への大きな一歩となります。
業務委託契約を締結する
外注先を最終決定したら、業務委託契約の締結に進みます。契約書には、業務の範囲や契約期間、報酬額、支払い条件、秘密保持、知的財産権の取り扱い、損害賠償など、重要な項目が明記されます。
契約内容は細部までしっかり確認し、不明点や懸念がある場合には、契約前に必ず双方で合意を形成しておきましょう。明確な契約は、後々のトラブルを未然に防ぎ、安心して業務を進めるための土台となります。
インフラエンジニア外注の注意点
インフラエンジニアの外注を成功させるには、事前準備から契約締結までのプロセスをしっかりと踏むことが重要です。
ここでは、外注先との信頼関係を築き、期待通りの成果を得るために押さえておきたい注意点をご紹介します。
契約内容はできるだけ具体的に定義する
契約書は、万が一のトラブルを防ぐための重要な基盤です。特に業務範囲(スコープ)は、「サーバー運用一式」といった曖昧な表現ではなく、「月次のOSパッチ適用」「障害発生時の一次対応と報告」など、具体的な作業内容まで明記することが重要です。
丸投げせず、適切な進捗管理を行う
外注先に業務を任せた後も、発注者としての関与は不可欠です。定期的な進捗報告の場を設け、課題や懸念点を早期に共有できる体制を整えましょう。外注先と「一緒にプロジェクトを進める」という姿勢が、良好な関係と成果につながります。
偽装請負にならないように注意する
特に準委任契約でSES企業などを利用する場合、発注者が外注先のエンジニアに直接指示を出すと「偽装請負」と見なされるリスクがあります。業務指示や勤怠管理は、必ず契約先の責任者を通じて行うようにし、法令遵守を徹底しましょう。
参考:東京労働局 | 偽装請負についてまとめ
本記事では、インフラエンジニアの外注に関する基本的な知識から、メリット・デメリット、費用相場、依頼先の選び方、注意点までを幅広くご紹介しました。
外注は、専門性の高い人材を柔軟に活用できる有効な手段であり、コストの最適化や業務効率の向上にもつながります。一方で、情報管理や契約内容の明確化など、慎重な対応が求められる場面もあります。
外注を成功させるためには、目的を明確にし、自社の課題に合った信頼できるパートナーを選ぶことが何より重要です。
ぜひ本記事の内容を参考に、貴社のIT戦略に最適な外注活用をご検討ください。