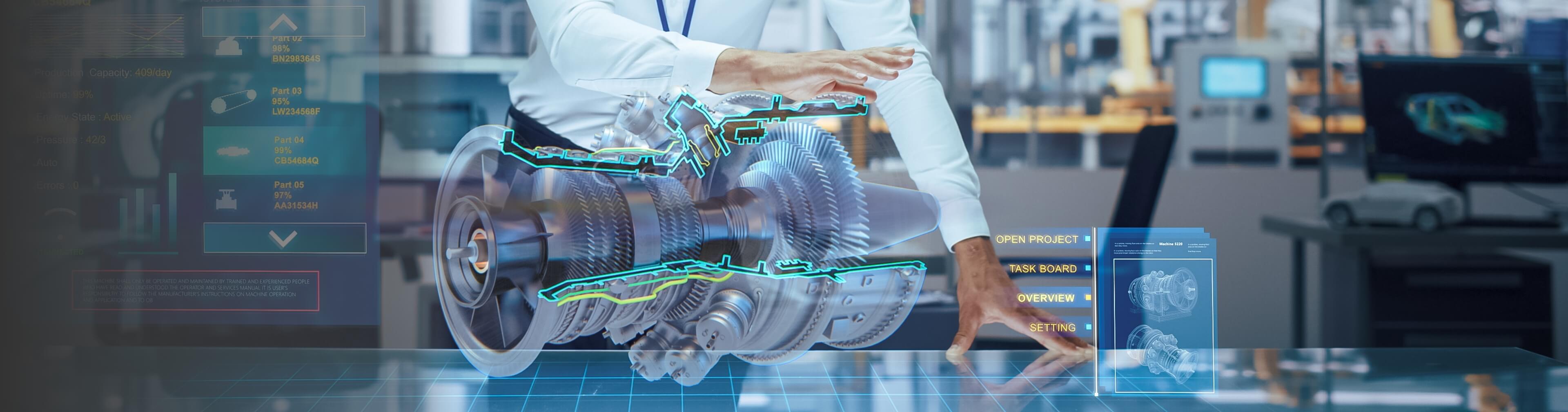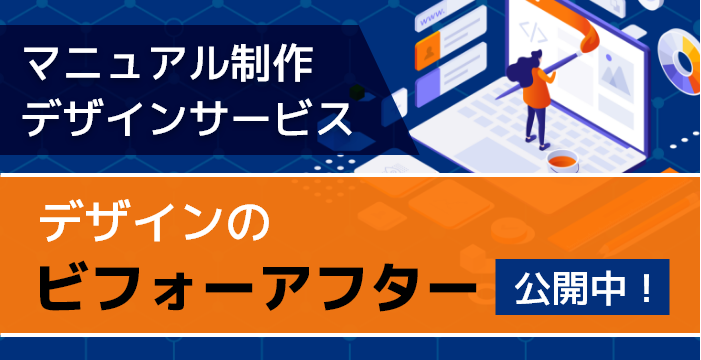業務請負契約書の作り方|委任契約との違い・印紙税・下請法まで徹底解説
2025.11.07
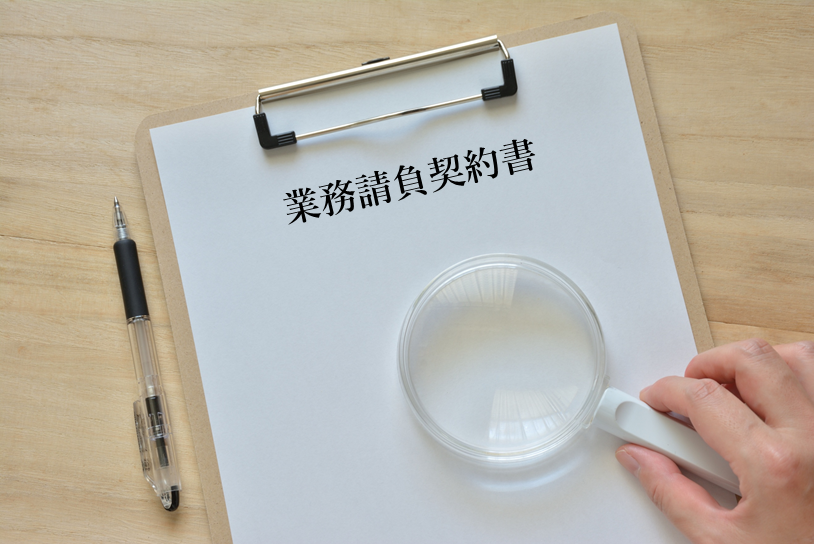
業務を外部に委託する際、トラブルを防ぐために欠かせないのが「業務請負契約書」です。
しかし、いざ契約書を作成しようとすると、「どのような項目を盛り込めばよいのか」「そもそも請負契約とは何か」といった疑問を抱く方も少なくありません。特に、専門の法務担当者がいない企業や個人事業主の方にとっては、契約書作成は大きな負担になりがちです。
この記事では、業務請負契約の基本的な仕組みから、契約書に盛り込むべき具体的な項目、作成時に注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。さらに、すぐに活用できる契約書のテンプレート(ひな形)もご用意しました。
この記事を読むことで、法的リスクを回避しながら、業務委託を円滑に進めるための実践的な知識が身につきます。
目次
業務請負契約とは?委任契約との違いをわかりやすく解説
業務を外部に委託する際、「業務委託契約」という言葉が広く使われますが、法的には「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」に分類されます。
まずは、これらの契約形態の違いについて正しく理解しましょう。
業務請負契約の定義
請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法第632条)。
最大の特徴は、「仕事の完成」が契約の目的である点です。例えば、Webサイトの制作、記事の執筆、ソフトウェアの開発などが典型的な例です。
業務委託契約との関係性
一般的に使われる「業務委託契約」は、法律上の正式な用語ではありません。「請負契約」や「委任契約(準委任契約)」の総称として使われることがほとんどです。
そのため、契約書を作成する際には、その実態が「請負」なのか「委任」なのかを明確にし、契約書の表題も「業務請負契約書」や「準委任契約書」とすることが望ましいです。
請負契約と委任契約(準委任契約)の比較
請負契約と委任契約の最も大きな違いは、契約の目的にあります。
以下の比較表で、請負契約と委任契約(準委任契約)の違いを整理しましょう。
| 項目 | 請負契約 | 委任契約・準委任契約 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 仕事の完成 | 事務処理の遂行 |
| 報酬の対象 | 完成した仕事(成果物) | 業務の遂行(労働時間など) |
| 契約不適合責任 | 負う | 原則として負わない |
| 善管注意義務 | 負う | 負う |
| 具体例 | Webサイト制作、システム開発、建築工事 | コンサルティング、受付業務、システム保守 |
委任契約は弁護士への訴訟代理の委任など法律行為を委託する契約であり、それ以外の事務処理を委託する契約は「準委任契約」と呼ばれます。
どちらも「業務の遂行」自体を目的としており、「仕事の完成」を義務付けられていない点が請負契約との大きな違いです。
なぜ業務請負契約書が必要なのか?作成の重要性とメリット

口頭での合意でも契約は成立しますが、後のトラブルを避けるために契約書の作成は極めて重要です。契約書は、当事者間の合意内容を明確にし、万が一の紛争を未然に防ぐ役割を果たします。
業務内容と成果物の明確化
「どのような業務を」「いつまでに」「どのような状態(品質)で」完成させるのかを具体的に定めることで、当事者間の認識のズレを防ぎます。特に、システム開発などでは、仕様を詳細に定義することが後のトラブル回避に繋がります。
報酬に関するトラブルの防止
「いくらを」「いつ」「どのような方法で」支払うのかを明記することで、報酬に関する紛争を避けられます。追加業務が発生した場合の報酬についても定めておくと、より安心です。
秘密保持義務の明確化
業務の過程で、自社の機密情報や顧客の個人情報を相手方に提供することがあります。秘密保持条項を設けることで、情報漏洩のリスクを低減させることができます。
すぐ使える!業務請負契約書のテンプレート(ひな形)
ここでは、様々な業務に汎用的に使える業務請負契約書のひな形(テンプレート)を紹介します。個別の取引内容に応じて、適宜修正してご活用ください。
汎用的に使える業務請負契約書のひな形
業務請負契約書
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と〇〇(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して委託する業務に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務の内容)
甲は、乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)〇〇の企画・設計
(2)〇〇の制作
(3)その他上記に付随する業務
第2条(契約期間)
本契約の期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。
第3条(報酬)
甲は、乙に対し、本業務の報酬として、金〇〇円(消費税別)を支払うものとする。
支払方法は、納品検収後、翌月末までに乙指定の銀行口座へ振り込む。
…(以下、各条項が続く)
留意事項
上記のひな形はあくまで一例です。実際の契約では、委託する業務の内容や当事者間の合意に基づき、条項を追加・修正する必要があります。
特に、成果物の仕様、検査方法、知的財産権の帰属などは、業務内容に合わせて具体的に定めることが重要です。不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
業務請負契約書に必ず盛り込むべき14の重要項目とは?
信頼性の高い契約書を作成するには、漏れなく重要項目を盛り込むことが不可欠です。ここでは、一般的な業務請負契約書に記載すべき14の項目を解説します。
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 業務の内容 | 委託する業務内容を具体的かつ明確に記載する。 |
| 2 | 契約期間 | 業務の開始日と終了日を明記する。 |
| 3 | 報酬(請負代金) | 金額、支払時期、支払方法を定める。 |
| 4 | 納品および検査 | 成果物の納品方法、検査期間、検査基準を明記する。 |
| 5 | 契約不適合責任 | 納品物に欠陥があった場合の修補や損害賠償について定める。 |
| 6 | 知的財産権の帰属 | 成果物に関する著作権などの帰属先を明確にする。 |
| 7 | 秘密保持 | 業務上知り得た情報の取り扱いについて定める。 |
| 8 | 個人情報の取り扱い | 個人情報を扱う場合のルールを明記する。 |
| 9 | 損害賠償 | 契約違反があった場合の損害賠償の範囲を定める。 |
| 10 | 契約解除 | 契約を解除できる条件を明記する。 |
| 11 | 反社会的勢力の排除 | 反社会的勢力との関係を一切持たないことを相互に確約する。 |
| 12 | 再委託 | 受託者が業務を第三者に再委託する場合の可否や条件を定める。 |
| 13 | 不可抗力 | 天災など、当事者の責に帰すことのできない事由による免責を定める。 |
| 14 | 管轄裁判所 | 紛争が発生した場合に、どの裁判所で審理を行うかを定める。 |
業務の内容
委託する業務の内容は、「〇〇の制作業務」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇に関する要件定義書の作成」「〇〇の機能を持つソフトウェアの設計・開発」のように、誰が読んでも誤解が生じないレベルまで具体的に記載することが重要です。
契約期間
業務の開始日と終了日を「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」と明確に定めます。プロジェクトの進捗に応じて期間が変動する可能性がある場合は、契約更新の条件や手続きについても定めておくと良いでしょう。
報酬(請負代金)
報酬の金額(税抜・税込)、支払条件(例:納品検収後、翌月末払い)、支払方法(例:銀行振込)を具体的に記載します。着手金の有無や、分割払いにする場合はその条件も明記します。
納品および検査
成果物の納品場所や方法、検収期間(例:納品後10営業日以内)を定めます。検査の基準や、検査に合格しなかった場合の対応(修正依頼など)についても明記しておくことで、納品に関するトラブルを防ぎます。
契約不適合責任(※旧称:瑕疵担保責任)
納品された成果物に、契約内容と異なる点(契約不適合)が見つかった場合に、請負人が責任を負うことです。注文者は請負人に対し、修正(追完)、代金減額、損害賠償、契約解除などを請求できます。この責任を負う期間をいつまでにするか、明確に定めておくことが重要です。
知的財産権の帰属
成果物に関する著作権や特許権などの知的財産権が、注文者と請負人のどちらに帰属するのかを定めます。一般的には、報酬の支払いと同時に注文者に移転すると定めることが多いですが、請負人が元々保有していた権利は留保されるといった例外を設けることもあります。
秘密保持
業務委託に伴い、相手方に自社の技術情報や顧客リストなどの秘密情報を提供することがあります。提供した情報が目的外に利用されたり、第三者に漏洩したりすることを防ぐために、秘密保持義務について定めます。
個人情報の取り扱い
業務上、個人情報を取り扱う場合には、その目的や範囲、管理方法などを厳格に定める必要があります。個人情報保護法を遵守した取り扱いを義務付ける条項を盛り込みます。
損害賠償
当事者のどちらかが契約に違反し、相手方に損害を与えた場合の賠償について定めます。賠償額の上限を設けるか否かなど、当事者間の力関係やリスクを考慮して決定します。
契約解除
相手方が契約内容を履行しない場合や、倒産した場合など、どのような場合に契約を解除できるのかを定めておきます。これにより、問題が発生した際に契約関係を円滑に終了させることが可能です。
反社会的勢力の排除
当事者が暴力団などの反社会的勢力ではないこと、また将来にわたっても関与しないことを相互に確約する条項です。現代の契約書では、コンプライアンスの観点から必須の条項とされています。
再委託
受託した業務の一部または全部を、別の第三者に委託(再委託)することを認めるかどうかを定めます。再委託を認める場合でも、「注文者の書面による事前の承諾を得ること」を条件とし、再委託先の選定責任や監督義務を元の受託者が負うことを明確にしておくのが一般的です。
不可抗力
地震、台風、戦争、テロといった、当事者の管理外の出来事によって契約の履行が困難になった場合に、その責任を免除する規定です。どのような事由が不可抗力にあたるのかを例示しておくと、解釈の余地が少なくなります。
管轄裁判所
万が一、契約に関して訴訟に発展した場合に、第一審の裁判を行う裁判所をあらかじめ指定しておく条項です。自社の所在地を管轄する裁判所を指定しておくことが一般的です。
契約書作成・締結時の注意点
契約書の内容を固めた後も、締結する際にはいくつか注意点があります。特に、印紙税や下請法との関連は重要です。
収入印紙は必要?不要?
業務請負契約書は、印紙税法上の「第2号文書」または「第7号文書」に該当し、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 |
※消費税の扱い:契約書に「消費税額が区分記載されている場合」は、税抜金額で判定できます。税込表記のみの場合は、税込金額で判定されます。
※軽減措置:建設工事請負契約など一部の契約書には、印紙税の軽減措置が適用される場合があります(令和9年3月31日まで延長中)。
ただし、契約期間が3ヶ月以内の継続的な請負契約(例:保守契約など)は第7号文書となり、一律で4,000円の印紙税がかかる場合があります。
下請法の対象になるケース
親事業者(発注者)の資本金が1,000万円を超え、資本金1,000万円以下の下請事業者(受注者)に委託する場合など、特定の条件下では下請法(下請代金支払遅延等防止法)が適用される可能性があります。
下請法が適用されると、親事業者には書面の交付義務、支払期日を定める義務、遅延利息の支払義務などが課せられます。自社の取引が該当しないか、事前に確認が必要です。
電子契約を活用するメリット
近年では、紙の契約書に署名・押印する代わりに、電子署名を用いた電子契約サービスを利用する企業が増えています。電子契約の場合、印紙税が課されないという大きなメリットがあります
郵送や書類管理の手間・コストを削減できるほか、契約締結までの時間も短縮できるため、業務効率の向上にもつながります。
まとめ|業務請負契約書を正しく作成してトラブルを防ぐ

本記事では、業務請負契約書の基本知識から、すぐに使えるひな形、記載すべき14の重要項目、作成時の注意点までを詳しくご紹介しました。適切な契約書を交わすことは、発注者・受注者双方の信頼関係を築き、円滑な業務遂行を支える重要なステップです。
本記事でご紹介した契約書のひな形やチェックリストは、業務請負契約を適切に締結するための有効な参考資料です。とはいえ、契約書の整備だけでなく、信頼できる人材の確保も業務委託を成功させるためには欠かせません。
「契約書は整ったけれど、適任者が見つからない」「専門スキルを持つ人材を探している」といった課題をお持ちの方は、BREXA Technologyの人材紹介サービスをご検討ください。
業務内容や契約形態(請負・準委任・派遣)に応じて、貴社の課題に最適な人材をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。