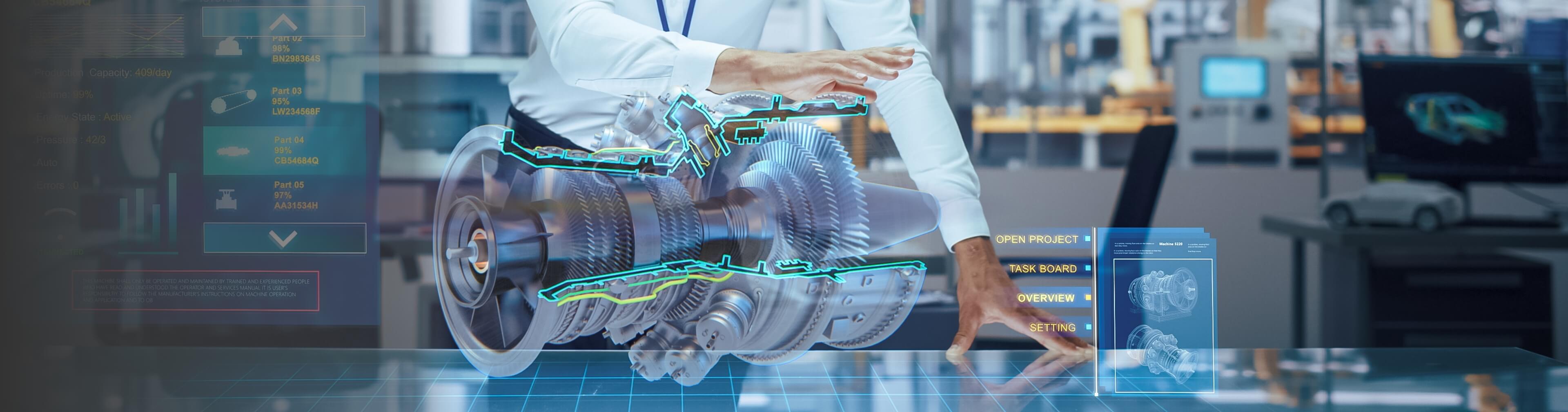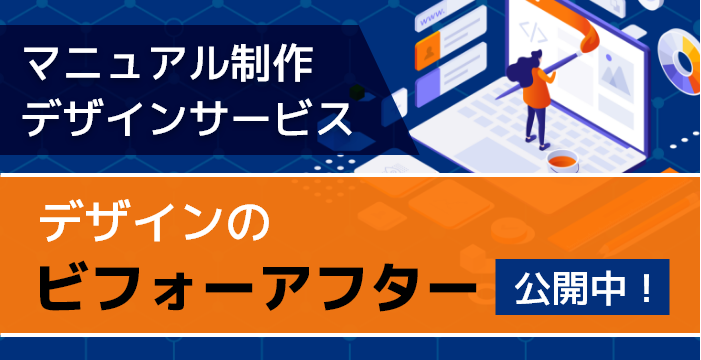請負とアウトソーシングの違いを徹底解説|自社に最適な委託契約の選び方
2025.10.07

業務効率化や専門性の確保を目的として、外部リソースの活用を検討する企業が増えています。
「アウトソーシング」や「請負」といった言葉を耳にすることは多いですが、その違いを正しく理解できているでしょうか?
両者は似ているようで、契約内容や法律上の扱いは大きく異なります。契約形態を正しく理解せずに進めてしまうと、「偽装請負」などの思わぬ法的リスクを招く可能性もあります。
この記事では、「請負」や「アウトソーシング」の代表的な契約形態である「準委任契約」との違いを中心に、それぞれのメリット・デメリット、自社に適した委託形態を選ぶためのポイントを分かりやすく解説します。
目次
請負とアウトソーシングの基本的な違いとは?
「請負」と「アウトソーシング」は混同されがちですが、それぞれの定義には明確な違いがあります。まずは両者の基本的な関係性を理解することが、適切な外部委託を行うための第一歩となります。
アウトソーシングとは外部委託の総称
アウトソーシング(Outsourcing)とは、自社業務の一部を外部の専門企業や個人に委託することです。
主にコスト削減や業務効率の向上、専門知識の活用を目的として導入されます。アウトソーシングを実現する契約形態として、法律上「請負契約」や「準委任契約」などがあります。つまり、アウトソーシングは外部委託という広い概念であり、「請負契約」はその中に含まれる具体的な契約形態の一つです。
請負契約は「仕事の完成」が目的
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が「仕事を完成させること」を約束し、もう一方(注文者)がその成果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。
典型的な例としては、システム開発、ウェブサイト制作、建物の建築などが挙げられます。注文者は、納品された成果物が契約通りの品質であることを確認し、問題がなければ報酬を支払います。ここで重要なのは、契約の目的が「仕事の完成」であるという点です。
準委任契約は「業務の遂行」が目的
一方、準委任契約は、法律行為以外の事務処理を委託する契約です。アウトソーシングでは、この準委任契約が用いられることがよくあります。
準委任契約の目的は、仕事の完成ではなく「業務を適切に遂行すること」そのものです。コンサルティング業務や、コールセンターでの顧客対応、システムの運用・保守など、成果物を明確に定義しにくい業務がこれに該当します。受任者は、善良な管理者として注意を払って業務を遂行する義務(善管注意義務)がありますが、成果物の完成までは求められません。
請負契約と準委任契約(アウトソーシング)の主な違い
請負契約と準委任契約の違いをより明確に理解するために、主要な項目を比較してみましょう。
| 項目 | 請負契約 | 準委任契約 |
|---|---|---|
|
契約の目的 |
仕事の完成 |
業務の遂行 |
|
報酬の対象 |
完成した成果物 |
業務の履行(労働時間や工数) |
|
指揮命令権の所在 |
受託者(請負人) |
受託者(受任者) |
|
善管注意義務 |
負わない |
負う |
|
契約不適合責任 |
負う |
原則として負わない |
契約の目的
前述の通り、最も大きな違いは契約の目的です。請負契約は「仕事の完成」を目的とし、準委任契約は「業務の遂行」そのものを目的とします。この目的の違いが、報酬の対象や責任の所在に影響します。
報酬の対象
請負契約では、報酬は「完成した成果物」に対して支払われます。 契約で定めた仕様通りのものが納品されなければ、原則として支払い義務は生じません。
一方、準委任契約では、業務を行った「行為(工数や時間)」に対して報酬が支払われます。そのため、期待した結果が得られなかったとしても、善良な管理者として業務を遂行していれば報酬を支払う必要があります。
指揮命令権の所在
どちらの契約形態でも、委託した業務に関する労働者への指揮命令権は、委託元(発注者)にはなく、業務を請け負った受託者(請負人・受任者)にあります。 委託元の担当者が、受託企業の従業員に対して直接、業務の進め方について細かく指示を出すことはできません。これを行うと「偽装請負」と見なされるリスクがあります。
善管注意義務の有無
善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、「その人の職業や社会的地位からみて、一般的に要求される程度の注意を払う義務」のことです。準委任契約では、受託者はこの善管注意義務を負います。 つまり、専門家として最善を尽くして業務を遂行する責任があります。
一方、請負契約にはこの義務はなく、代わりに成果物を完成させる義務を負います。
契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の有無
請負契約では、納品された成果物に契約内容と異なる点(不具合や欠陥など)があった場合、請負人が責任を負います。これを契約不適合責任(※2020年の民法改正により、従来の瑕疵担保責任から変更された概念)といい、注文者は修正や代替品の請求、損害賠償請求などができます。
一方、準委任契約では業務の遂行が目的であるため、原則としてこの責任は発生しません。
請負契約のメリット

成果物の完成を目的とする請負契約には、発注者にとって以下のようなメリットがあります。
成果物に対して報酬を支払うためコスト管理がしやすい
請負契約は、「この制作物にいくら」という形で契約するため、コストが明確です。成果物が完成し、検収が完了するまでは支払いが発生しないため、予算管理がしやすいという大きなメリットがあります。
専門性の高い業務を高品質で完遂してもらえる
請負事業者は、特定の分野における専門的なノウハウや技術を持っています。 自社にない専門性を活用し、高品質な成果物を得ることが期待できます。また、成果物の品質に責任を持つため、質の高いアウトプットが保証されやすい点も魅力です。
請負契約のデメリット
一方で、請負契約には注意すべきデメリットも存在します。
業務の進め方を直接指示できない
メリットであると同時にデメリットにもなりうるのが、指揮命令権がない点です。
業務の進め方は完全に請負事業者に一任されるため、「もう少しこうしてほしい」といった細かな要望やプロセスへの介入はできません。もし指示を出してしまうと、後述する「偽装請負」を疑われる可能性があります。
仕様変更への柔軟な対応が難しい
請負契約は、最初に定めた仕様書に基づいて成果物を作成します。そのため、途中で仕様変更や追加の要望が出た場合、別途追加の契約や費用が必要になることがほとんどです。柔軟な変更には対応しにくい側面があります。
準委任契約(アウトソーシング)のメリット

業務の遂行を目的とする準委任契約には、以下のようなメリットが挙げられます。
業務プロセスの改善が期待できる
準委任契約では、専門家が業務プロセスそのものに関与します。そのため、自社だけでは気づかなかった非効率な点を発見し、業務フロー全体の改善提案を受けられる可能性があります。単なる労働力の提供だけでなく、業務の質的向上も期待できます。
仕様変更や業務量の変動に柔軟に対応できる
準委任契約は、時間や工数をベースに契約することが多いため、業務内容の変更や業務量の増減に比較的柔軟に対応できます。市場の変化が激しい業務や、プロジェクトの進行によって依頼内容が変わる可能性がある場合に適しています。
準委任契約(アウトソーシング)のデメリット
メリットの裏返しとして、準委任契約には以下のようなデメリットも考えられます。
成果物の完成が保証されない場合がある
準委任契約の目的はあくまで業務の遂行であり、成果物の完成を保証するものではありません。 したがって、受託者が善管注意義務を果たして業務を行っていれば、たとえ期待した結果が得られなくても報酬を支払う必要があります。
社内にノウハウが蓄積しにくい
業務を外部に任せきりにしてしまうと、その業務に関する知識や経験が社内に蓄積されにくいというデメリットがあります。 契約が終了した際に、自社で対応できる人材がいないという事態に陥る可能性も考慮しておく必要があります。
【重要】注意すべき「偽装請負」とそのリスク
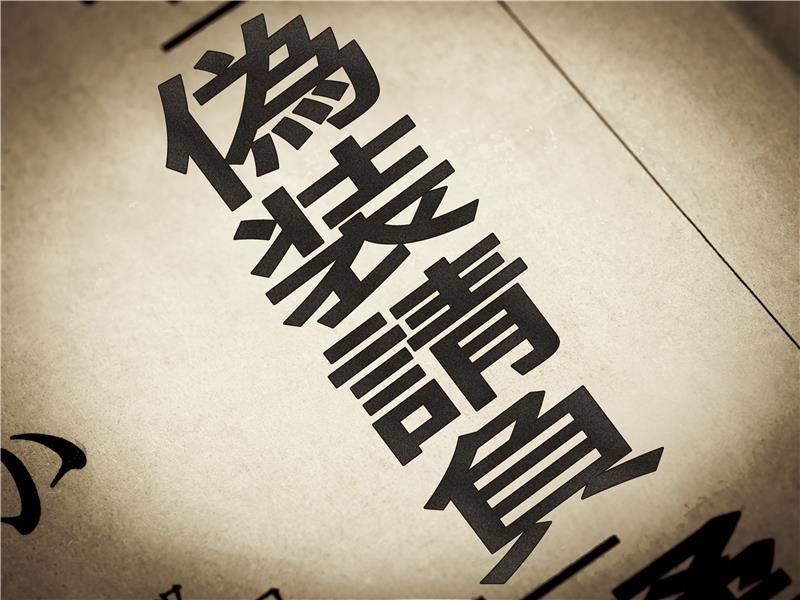
アウトソーシングを検討する上で、絶対に避けなければならないのが「偽装請負」です。これは法律違反であり、厳しい罰則の対象となります。
偽装請負とは何か?具体的な判断基準を解説
偽装請負とは、契約形式上は請負(または準委任)契約でありながら、実態としては労働者派遣に該当する状態を指します。判断基準の中でも特に重要なのが、「発注者が受託者の労働者に対して、直接指揮命令を行っているかどうか」という点です。例えば、以下のようなケースは偽装請負と判断される可能性が非常に高いです。
- 発注元の社員が、委託先企業の従業員に業務の進め方を直接指示している。
- 始業・終業時刻や休憩時間、休日などを発注元が管理・指定している。
- 発注元が委託先企業の従業員の配置や人事評価に関与している。
偽装請負と判断された場合のリスク
偽装請負は、職業安定法や労働者派遣法、労働基準法に違反する行為です。発覚した場合、発注者・受託者の双方が罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金など)を受ける可能性があります。
また、行政指導や企業名の公表など、社会的信用の失墜につながる重大なリスクを伴います。
請負と準委任、どちらを選ぶべきか?判断のポイント

自社にとってどちらの契約形態が最適かを見極めるためには、以下の3つのポイントを検討することが重要です。
成果物を明確に定義できるか
委託したい業務の「成果物」が、仕様や数量、品質などを含めて明確に定義できる場合は「請負契約」が適しています。 一方で、ウェブサイトの運用・保守やコンサルティングのように、成果物を一つに特定しにくい業務は「準委任契約」が向いています。
業務プロセスへの関与をどの程度求めるか
業務の進め方や品質管理をすべて専門家に任せ、完成した成果物だけを求めるのであれば「請負契約」が良いでしょう。逆に、業務の進め方について定期的な報告を受け、ある程度プロセスにも関与しながら進めたい場合は「準委任契約」が適しています。
委託したい業務の範囲は固まっているか
プロジェクトの開始から終了まで、委託する業務の範囲や内容が完全に固まっている場合は「請負契約」がスムーズです。しかし、開発途中で仕様変更が発生する可能性が高い場合や、月々の業務量に波がある場合は、柔軟に対応しやすい「準委任契約」が有利です。
信頼できるアウトソーシング先の選び方

適切な契約形態を選んだとしても、パートナーとなる委託先の選定を誤れば、期待した効果は得られません。以下の点をチェックして、信頼できる委託先を選びましょう。
委託したい業務分野での実績は豊富か
委託を検討している業務分野において、豊富な実績や成功事例があるかを確認しましょう。 公式サイトの導入事例をチェックしたり、具体的な実績について問い合わせたりすることが重要です。
セキュリティ体制は万全か
業務を委託するということは、自社の機密情報や個人情報を外部に渡す可能性があるということです。 情報漏洩は企業の信頼を根底から揺るがす重大なリスクです。プライバシーマークやISMS認証などの第三者認証を取得しているか、具体的なセキュリティ対策について明確な説明があるかを確認しましょう。
円滑なコミュニケーションが可能か
外部に業務を委託するとはいえ、良好なパートナーシップを築くためには円滑なコミュニケーションが不可欠です。報告・連絡・相談の体制が整っているか、担当者との相性は良いかなど、契約前にしっかりと見極めることが成功のための重要な要素となります。
まとめ
本記事では、「請負契約」と「準委任契約(アウトソーシング)」の違いについて、契約の目的、指揮命令権、責任の所在といった観点から解説しました。請負契約は「成果物の完成」を目的とするのに対し、準委任契約は「業務の遂行」を目的としています。この違いを正しく理解することで、偽装請負のリスクを回避し、外部リソースをより効果的に活用することが可能になります。
委託したい業務の内容や目的を明確にしたうえで、それぞれの契約形態のメリット・デメリットを比較検討し、自社にとって最適なパートナーと契約を結びましょう。
準委任契約をご検討の際には、専門性や対応力に優れた人材を柔軟に活用できる選択肢として、フリーランス人材の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。BREXA Technologyでは、フリーランス支援サービス「エンベスト」も提供しており、委託内容に応じた人材のご提案が可能です。
業務委託の形態に迷われた際や、技術人材の活用に課題を感じている場合は、ぜひBREXA Technologyおよびエンベストにご相談ください。